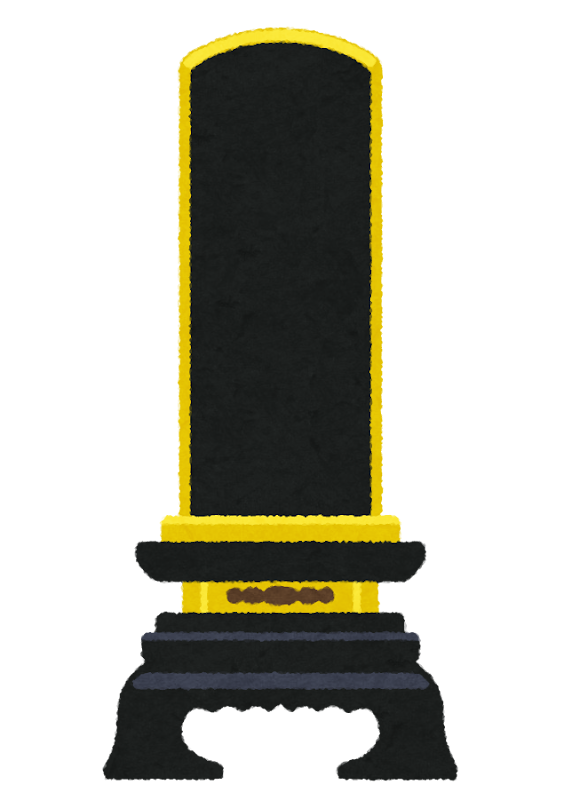興運堂福島店のお仏壇・仏具マメ知識⑦「お位牌の種類」
お位牌は大きく分けて、ご葬儀の際に使われる白木位牌(内位牌)、四十九日以降にお仏壇に祀る本位牌、お寺に祀る寺院位牌があります。
本位牌は、漆を塗った「塗り位牌」、黒檀や紫檀などから作られた「唐木位牌」、ライフスタイルに合わせた現代的なデザインの「モダン位牌」など、種類は様々です。
お位牌選びにお困りでしたら、お気軽に興運堂福島店までお問い合わせください。
白木位牌とは
白木位牌とは、葬儀や四十九日法要までに使用する仮の位牌のことです。
仏教では、亡くなった人の魂が四十九日までに成仏すると考えられています。その間、魂は白木位牌に留まるという考え方から、四十九日法要まで白木位牌を使用します。
主にスギやヒノキで作られ、四十九日法要が終わると本位牌と入れ替え、お寺で魂を抜く「閉眼供養」を行い、お焚き上げで処分されるのが一般的です。
寺院位牌とは
寺院に安置する位牌のことを指します。
通常、お位牌は自宅の仏壇に安置されますが、故人の霊を祀り、供養するためのもので、自宅に位牌を安置できない場合や、永代供養を希望する場合などに、寺院に故人の霊を祀ってもらうための位牌です。
寺院によって費用や条件が異なるため、事前に確認することが重要です。
四十九日法要とは
四十九日法要とは、故人が亡くなってから49日目に行われる仏教の法要のことです。
故人が無事に成仏し、極楽浄土へ行けるように祈る儀式で、忌明けの法要としても知られています。
仏教では、人は亡くなってから7日ごとに閻魔様による裁きを受け、49日目に最後の裁きを受けて極楽浄土へ行けるかどうかが決まると考えられています。
そのため、四十九日法要は故人が無事に成仏し、極楽浄土へ行くことができるように、遺族が供養と祈りを捧げる重要な儀式とされています。
閻魔様とは・・・
閻魔様(閻魔大王)は、仏教において冥界を司り、死者の生前の罪を裁く王として信仰されています。
元々は古代インドの神ヤマが仏教に取り込まれ、冥界の王として伝えられました。地獄のイメージが強いですが、仏教では全ての存在を救済したいと願う存在でもあります。
四十九日法要の流れ
おおまかな四十九日法要の流れは以下の通りです。
- 僧侶の読経:僧侶が読経を始め、焼香を行います。
- 法話:僧侶が法話をして、故人の霊を慰めます。
- 納骨 (希望する場合):納骨を行う場合は、法要後に墓地へ移動し、僧侶の立会いのもと納骨を行います。
- 会食 (お斎):法要後、参列者と共に会食を行い、故人を偲びます。
- 施主の挨拶:最後に、施主が参列者へ感謝の挨拶をします。
四十九日法要の準備
- 日程調整:菩提寺の僧侶と相談し、親族が集まりやすい土日などを選んで日程を決定します。
- 場所の選定:自宅、寺院、葬儀場、ホテル、料理店など、参列者の都合に合わせて場所を決めます。
- お布施の準備:僧侶へのお礼として、お布施を準備します。
- 引き出物の準備:参列者へのお礼として、引き出物を準備します。
- 本位牌の準備:故人の魂を込める本位牌を準備します。浄土真宗の場合は、位牌の代わりに過去帳に法名などを記載します。
- その他:挨拶状、会食の手配、返礼品、服装なども事前に準備します。
四十九日法要のマナーなど
- 服装:遺族は正喪服または準喪服、参列者は略喪服を着用します。
- 香典:香典は、故人との関係性や年齢によって金額を考慮し、奇数で包むのが一般的です。
- お供え物:お供え物は、故人の好物や、お花、お菓子、果物などが一般的です。
- その他:法要前後の挨拶、遺品整理、形見分けなども、事前に準備しておきましょう。
※正喪服・・・遺族や故人に近い親族が着用する、最も格式の高い喪服です。男性はモーニングコート、女性は喪服ワンピースやスーツなどが一般的です。
※純喪服・・・弔問客が着用する一般的な喪服です。男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマル(ワンピースやスーツなど)が一般的です。お通夜や葬儀、法事に着用します。
※略喪服・・・三回忌以降の法要や急な弔問、お通夜の時に着用する、より控えめな喪服です。男性はダークスーツ、女性はワンピースやスーツなど、黒や紺などのダークカラーで控えめな服装であれば失礼にはなりません。
その他
- 四十九日法要の香典は、葬儀の香典よりもやや少なめに包むのが一般的です。
- 香典の金額は、地域や家庭によって異なる場合があるため、周囲の方と相談して決めるのが良いでしょう。
- 香典袋の表書きは、「御仏前」または「御霊前」とします(浄土真宗の場合は「御仏前」)。
- 香典袋の水引は、黒白または双銀の結び切りを使用します。
- 香典を渡す際は、袱紗に包んで渡すのがマナーです。